越谷ゴルフです。
「スコアの現実⑩」で、
事件は会議室で起きているのではない。現場で起きているんだ!
を少しひねって、
ゴルフコースという現場では理論は役に立たないという表現をし、
結局「必要なことを行動すれば結果は出る」ということを述べました。
つまり、
「ゴルフができる人は具体的にどんな行動をとっているか」
これを研究した理論があるので紹介しておきましょう。
逆に言うと、練習場という会議室的な場所のほうが
こういう分析は向いているのです。
1970年代にハーバード大学のマクレランド教授が、
アメリカ国務省から依頼され、外交官の業績格差についての
調査、研究をしたもので、
「業績の高さと学歴にや知能にはあまり相関関係はない。
しかし、高業績者にはいくつかの共通の行動特性がある。」
という報告をしており、これを、「コンピテンシー理論」 と
いいます。
コンピテンシーにおけるゴルフマネジメントは、
ゴルフにおける高業績者が何をしているか、のあくまで具体的な
行動そのものをみていくことになります。
この理論をあなたの会社の人事部が採用しているかもしれません。
従来の、能力主義人事制度の評価基準では、
「○○することができる」という評価項目をクリアーしていけば
実績を残していなくても資格を多くとっていけば
潜在的な能力があるとして昇進していたのですが、
コンピテンシーにおける人事評価では、
「高い業績を残すために、具体的に○○しているか」
というプロセスにも焦点をあてて人事評価しています。
つまり、普段の何気ない行動まで問われているのです。
「具体的に○○している」というモデルは、
あらかじめ高業績者に詳細なインタビューを行い、つくられます。
コンピテンシーを「評価基準」にした場合は、
営業職を例にあげると、
「なぜそうなったのか」というプロセスが明確になります。
どんな「行動」が不足していたか、違っていたか、といった部分が
把握しやすいので、次に高い営業成績を残すための
「行動基準」にもなるのです。
ゴルフでも、コンピテンシーを評価基準として
「自分が何をしているか」知るために使え、
「行動基準」として「何をすればいいのか」
を知るために応用できることでしょう。
これが、「必要なことをやっているか」の部分であり、
高業績者に共通するコンピテンシーモデルを知ることが
「うまくなるには何をすればいいの?」
への第一歩となると思います。
●●●●●●●●●●
越谷ゴルフリンクス
越谷市大間野町1-155
http://www.koshigayagolf.com

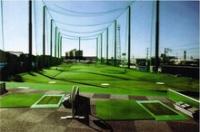 ●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●